すべてはフィクションであり、実在の個人・団体等にはいっさい関係ありません。

|
拝殿 |
時代により、規模を増した。今村忠彦氏の見識どおり、この建物は初めから拝殿として造られ、回廊は後世に付け加えられたものである。
しかし、神聖視されているのは“土地”でも“地中に埋まる柱”でもなく、地下室である“本殿”。様式として大変に珍しいが、かつてその部屋にて榊茂(初代媒介者)を守っていたという伝統から、そのように造られる。当初の神は、必ず榊茂の元へ帰ってくる(降臨する)ので、不動の社殿(掘立柱)となった。“床下の隠蔽”、立入制限、撮影禁止は、おおむね本殿の存在を隠すためである。とくに床下は、排気口等がでているので隠蔽する他はない。
本殿
拝殿の規模、および建築技術の向上により、規模を増した。拝殿の床に土間を足した床面積をもつ。先の修造のさい、地下は完全に鉄筋コンクリート建築とされた。地面と本殿の間に、地下の照明や冷暖房をになう機械室がある。吸排気は拝殿の後方床下からおこなう。電気は地下ケーブルで引いている。水の供給はない。
本殿の存在が隠されている理由は、神秘性の保護、さらに非公開神事の保護である。こと神事は悪天候であっても怠れぬものが多く、また、現代のモラルには反するものも含まれる。しかも、それらが出席した神官以外の目にふれることは、宗教理念において厳禁である。そのため、当初は榊茂を隠す目的だった本殿は、そのまま存在そのものを隠すこととなった。また過去には、国政などに止むを得ず違反する場合、一時的に物品(人は不可)などを保管することもあった(例:GHQの刀狩り)。こと現在では人工衛星技術が進んでいるので、別棟でなく地下室だったことは幸運といえる。
出入りは、拝殿の奥中央にある床扉から行う。扉開閉における電動・手動手段とも、目視できぬよう床や柱の内にカモフラージュされている。また平時であれば、開閉にかかわらず扉の周囲は御簾で覆われている。扉は、左横にスライドして(車輪付き後方を突き出た前方が押す形で)開く。階段は幅2m、右へと下りる。左側1m〜3mの高さの壁に、木彫りの彫刻によるレリーフがある。建物を半周した拝殿土間の直下が、本殿入口となる。
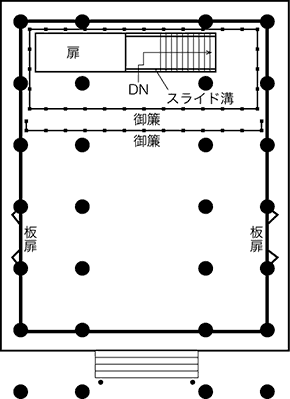
|
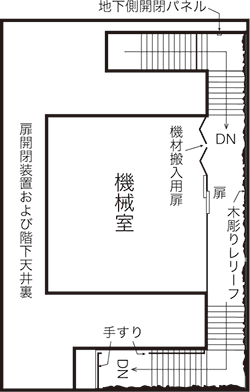
|
榊茂の間から先は、宗教理念において神域と定義され入室制限があるが、掃除などは宰神司直属の正神修たちが“不可視者(あらざるもの)”として担う。また太古からの習わしで、榊茂の間は季節ごとに“榊茂が暮らしているような”支度がほどこされるが、それも彼らが行う。そのための道具、現在では骨董品に類する丁度品や衣類は、左右の宝物室に保管されている。
神座には、これまでの榊茂・宰神司の遺骨が祀られている。
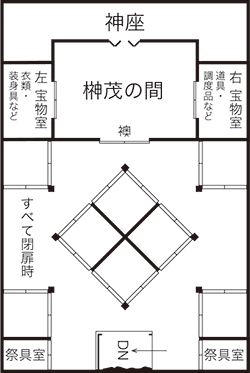
|
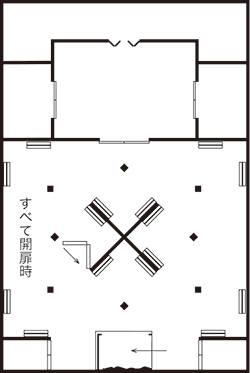
|